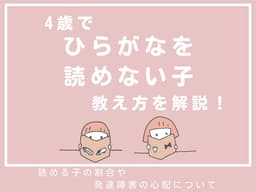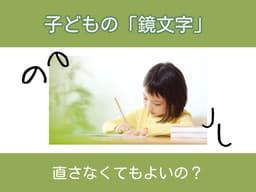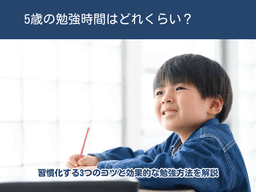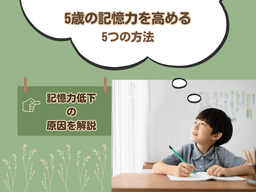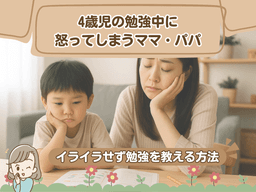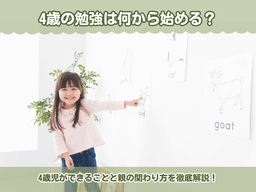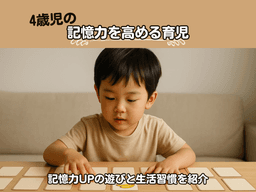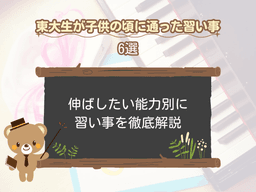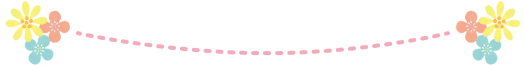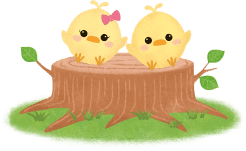子どもはいつからひらがなを読むようになる?
まずは、一般的に子どもが何歳くらいからひらがなを読んだり書いたりするようになるのか、時期別にその過程を見ていきましょう。ただし、詳しくは後述しますが、文字の読み書きの習得は個人差が大きく、遅れていても基本的に大きな心配はいりません。
ひらがなを「読む」時期ごとの目安は以下になります。
2歳から3歳ごろ
この頃から言葉の理解が進み、簡単なひらがなや単語を聞き取ることができるようになります。子どもによっては遊びやおもちゃを通じて、基本的なひらがなを見分けられるようになってきます。
4歳から5歳ごろ
幼稚園や保育園でひらがなに触れる機会が増えたり、絵本やカードを用いた遊びを通じて、ひらがなの音や形に慣れ親しむようになり、この時期にひらがなを読める子が増えてきます。
小学校入学前(6歳前後)
保育園や幼稚園によっては、小学校に入学する前にひらがなの読み書きが本格的に教えるところもあります。簡単な言葉や文を理解し、自分で読んで表現できるようになります。
子どもはいつからひらがなを書くようになる?

読むことと同様にひらがなを書くことも、子どもの発達には個人差があります。しかし、多くの子どもが3歳から6歳の範囲である程度のひらがなを書けるようになります。以下は、早い子の場合の一般的な進行を示すものですが、これはあくまで目安であり、多少ひらがなを書くのが遅くても大きな心配は不要です。また、読み・書きでいうと、まずひらがなを読めるようになるのが先で、書けるようになるのはその後になります。
3歳前半
まだひらがなを書くことは難しいですが、視覚的に文字を見て認識できるようになります。必ずしもさせる必要はありませんが、文字をトレースしたりすることで手の動きを覚えることができます。
4歳前半
ある程度のひらがなを書くことができるようになります。まずは単純な文字や自分の名前を教えてあげるとよいでしょう。
5歳以降
「音韻認識(※)」といわれる、言葉が音の組み合わせでできているという認識が子どもに生まれる時期で、この時期に子どもは文字の理解が進み、ひらがなもより書けるようになります。
※例えば「みかん」が「み」と「か」と「ん」の3つの音に分けられると認識できること
ひらがなを書くことについては、早くできるに越したことはありませんが、小学校入学時点で自分の名前が書ければ十分くらいに構えてあげてください。それよりも3~6歳の幼少期にはするべきことがたくさんあります。
合わせて読みたい
子どもにひらがなに興味を持ってもらうには?

とはいえ、やはり子どもにある程度ひらがなを覚えてほしい!と感じている親御さんもいらっしゃると思います。子どもにひらがなを教える際にもっとも大切なことは、強制せずに子どもが楽しいと感じる範囲で教えることです。また、できなくても怒ったり落胆したりせず、できた時はたくさんほめて自信をつけさせることも重要です。
その大前提をふまえたうえで、子どもがなかなかひらがなに興味を持たない場合、以下のアプローチを試してみることが役立つかもしれません。
ゲームや楽しい遊びのなかで伝える
子どもたちが楽しんで学べるようなゲームや遊びのなかでひらがなに興味を持たせましょう。ひらがなの文字を使ったカードゲームや、絵本を読みながら楽しい歌を歌うことで、学習が楽しいものになります。
子どもの興味を引くテーマを取り入れる
子どもの好きなキャラクターやテーマを取り入れてひらがなを教えると、興味を引きやすくなります。例えば、好きなアニメや絵本のキャラクターがひらがなで表現されているようなものを使うと、子どもは楽しみながらひらがなにも興味を持つようになります。
子どもと一緒に遊ぶ
両親も一緒に遊びに参加して、楽しみながらひらがなを学ぶことが大切です。親子で一緒に文字を書いたり、言葉遊びを楽しむことで、子どもは学びをポジティブなものとしてとらえるようになります。
子どものペースを尊重する
子どもがまだひらがなに対する興味を持たない場合、無理に学ばせるのではなく自分のペースを尊重しましょう。子どもが自分から学びたいと思う気持ちが芽生えるのを待つことが重要です。
ママやパパと一緒に、楽しくひらがなに触れていくことが大切です♪

子どもにひらがなを教える際のNG事項

子どもにひらがなを教える際、いくつかのNGなことがあります。基本的には強制すること、怒ったり落胆することなど過度な期待をすることです。子どもは楽しいことは自らいくらでもしたがりますが、嫌なことは強制してもほとんどやろうとしません。あくまで、子どもにとって楽しい体験にしてあげることが大切です。
無理やり覚えさせる(強要する)
子どものペースに合わせず、無理に覚えさせることは避けましょう。くり返しになりますが、子どもが自分のペースで学ぶことが大切です。
叱る・落胆する
間違ったからといって叱ったり、親が落胆している様子を見せると、子どもがひらがなに対してネガティブなイメージを持つようになります。逆にできた時はたくさんほめてあげたり一緒に喜ぶことで、学びの時間が楽しいものになります。
単語や文字の意味を無視する
ひらがなを単なる記号として教えるのではなく、それぞれの文字や単語の意味や使い方にも触れるようにしましょう。文脈を通じて意味を理解することで、より理解がすすみます。
一方的に教える
親が子ども一方的に教えるのではなく、子供の興味や好奇心を尊重し一緒にお話をしながら学ぶ機会を増やしましょう。
長時間無理に教える
子どもの集中力の限界は、大人が考えるよりずっと短いものです。長時間一度に無理に学習させるのではなく、短い時間で集中して学ぶことが効果的です。子どもを疲れさせないように心がけましょう。
他人と比較する
兄弟姉妹や友達と比較したり、競争させたりすることは絶対に避けましょう。子どもはそれぞれ自分のペースで成長するものです。比較はプレッシャーにしかならず、文字の読み書きにかぎらず子供にとってプラスとなることはありません。
まとめ:ひらがなができなくも焦る必要なし。子どものペースを尊重しよう

いかがでしたでしょうか?
先述しましたが、幼児の時期に文字の読み書きができるに越したことはありませんが、成長には個人差が大きく、この時期にできるか否かはあまり影響はありません。また、教える際も強制したり怒ったりせず、子ども自身がポジティブに楽しく取り組めるようにすることが大切です。
親としては、周りの子どもたちと比較して変に焦ったりせず、子どもの可能性を信じて楽しい経験や自信をつけさせてあげるように注意しましょう。
合わせて読みたい
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #子ども #幼児 #ひらがな #興味 #教える #いつから

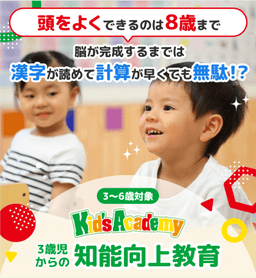

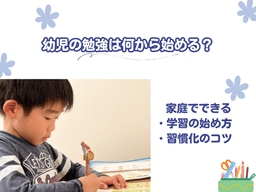
.png&w=256&q=75)