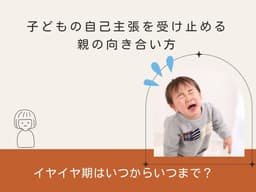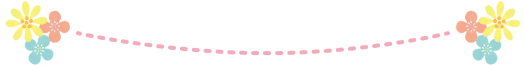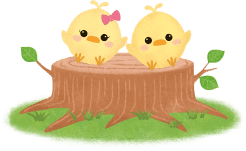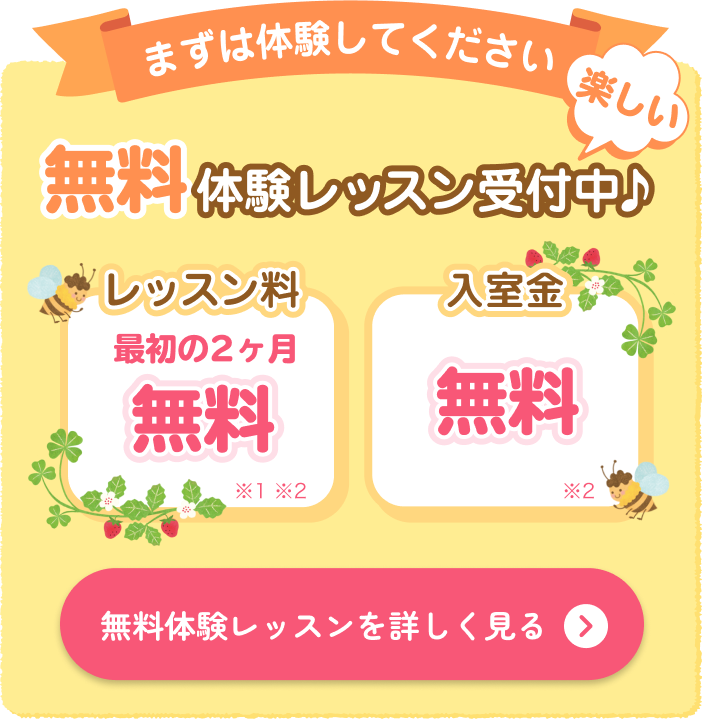「躾(しつけ)」とはいったい何か?
「躾(しつけ)」とはいったい何でしょう。言葉というものは時代とともにに大きく変化し、またその人の人生経験や生育歴においても一つの言葉に対するイメージは十人十色に違うものです。
「躾(しつけ)」の語源について
しつけの最も古い語源は、仏教用語の「習気(じっけ)」だといわれます。習気とは「習慣性」を指す言葉であり、行動習慣や思考習慣が深層心理を超えた魂のレベルにまで溜まるような意味を表しています。
転じて、田んぼの稲やお裁縫の縫い目をまっすぐにするための手法を「しつけ」と呼ぶようになったり、集団社会でのルールやマナー、慣習などを子どもの身につけることを指すようになったりと、概念が拡大してきました。
しつけのための「手段」は、しつけではない

この数百年の間には、しつけのための手段のことをも、「しつけ」と考える人も増えています。虐待に近い体罰を「しつけと思ってやった」と答える大人が時々いるのも、「しつけ」を手段という意味で使っている例であり、「しつけ」という言葉が好きになれないという人の多くは厳しい訓練や押しつけがましい強制をイメージされることが多いものです。
「しつけとは何か?」を考える時、拡大解釈の結果である「手段」の部分は分けて考えた方が育児の本質を見つめやすいでしょう。
躾の概念を見直し、これからの子どもたちへ何を躾けていくべきなのかを考えてみると良さそうだね!

しつけとは「子どもが幸せに生活できるための行動習慣を育てること」
ベビーパークでは、「しつけとは、子どもが人間社会で独り立ちして、幸せに生活できるための行動習慣と思考習慣を育てること」と定義しています。
3歳未満はそれほど高度な思考力が育っていないため、ここでは「行動習慣」についてお伝えいたします。「行動習慣」と言えば、はみがき、着がえ・手洗いなどの基本的生活習慣と、あいさつや礼儀作法などの社会的マナーが中心となるでしょう。
まずは、親が生活習慣やマナーの明快な基準を持つことが大切
しかし、実際には多くの親たちが自分の中で生活習慣や社会的マナーの明快な基準を持っていないことが多く、ただなんとなく「これが良いのだろう」というイメージを漠然と持っている状態であることがほとんどです。そのため世間に氾濫する大量の情報によって不安になったり、悩んだりしがちになります。そして、お子さんが親の深層心理にある漠然とした「理想の子ども像」と違う行動をした時に、イライラしたり怒りの感情が沸き起こったりしてしまうのです。
漠然とした「子どもはこうするのが当たり前」を考えなおす
適切なしつけをおこなうには、まずこの漠然とした「理想の子ども像」のイメージを壊してしまう事が一番です。そのためには自分の中の「子どもはこうするのが当たり前」というイメージを言葉で書き記して明快にしてみるとよいです。そして、書き出した「当たり前」はいったい一般的にどれくらい当たり前なのか?を改めて考えてみましょう。
例えば、「早寝早起きをする」とはいったい何時くらいが早寝であり早起きなのか?、職業によっても違うし、住んでいる地域や国、さらには時代によっても違ってくるでしょう。
「はみがきをする」というのは毎食後なのか?それとも一日に何回なのか?
「走らない」とはどういう場所でのことか?
など、改めて考えてみると、私達がおぼろげに「常識」と思いこんでいたものは、実は非常に狭い範囲内での慣習だったことに気づきます。場所が変わり、年代が変われば、常識などというものはいくらでも変わっていくのです。

他人と比較せず、各家庭で生活習慣の基準をもつ
よって、基本的生活習慣のルールは各家庭で基準をもつことが大切です。他人と比較しても仕方がなく、これが究極のベスト、というものもありません。まずは自分の頭の中から「当たり前」という概念を捨て去りましょう。自分の当たり前は、他の誰かの当たり前ではないかもしれないのです。
具体的なしつけの方法
そして実は、効果的なしつけの中の、とても大切で一番最初におこなわなくてはならない方法を実践するには、この「ご家庭の基準」をしっかり持っている必要があります。3歳未満対象のしつけ方法の項目は下記です。
1.親が生活習慣の家庭基準をはっきり示す。よき見本を見せ続ける。
2.生活習慣の基準を壊す悪習慣をおこなえないよう、環境を改造する。
3.子どもの望ましくない行動は先回りしてガードする。
4.子どもが望ましい行動をした瞬間に敏感に気づき、褒める。
5.子どもが望ましくない行動をした時は、何事もなかったように無反応のふりをしつつ、同じ行動ができないようさりげなくガードする。
6.「走る」「登る」「いろいろ触る」など子どもの本能から生じる行動は極力妨げずにすむ環境を用意してあげる。
7.子どもに「ありがとう」を伝えられる状況に敏感になる。
8.子どもの行動に対して「私はどう感じたか」を伝える機会を増やす。

命令や禁止、叱ることはしつけにつながらない
上記には、指示や命令、禁止や叱ることは含まれておりません。「指示と命令」はその事柄を習慣付けるどころか、逆に大嫌いにさせる効果があります。また「禁止すること」は、その事柄をやってみたい欲望を掻き立てます。
したがって、逆にやらせたいことや習慣づけたいことをあえて一定期間禁止するという方法は、高度なしつけの技術となります。そして「叱る」という方法は言語と知能が充分に育ち、かつ愛着関係・信頼関係が育っていないと効果がありません。
しつけとは子どもに何かをさせることではなく、親が手本を見せ続けること
実は最も基本のベースとなるしつけ方法は、「親が家庭内の生活習慣基準を守ること。その姿を時間をかけて見せ続けること」なのです。子どもに何かさせることだと思いがちですが、そうではなく、親が明快に基準の手本を毎日根気良く見せ続けることです。そのためには、夫婦の間でも生活習慣基準がハッキリしている必要があります。
乳幼児期の子どもには「しつけをさせること」をまだ考えない
そして「子どもにしつけをさせること」は今の段階ではまだ考えないようにしましょう。なぜなら、望ましい生活習慣がしっかりと確立してくる時期は、女の子が5歳から7歳、男の子は7歳から9歳頃、さらにお子さんのタイプによっては9歳から11歳くらいになることもあります。
これは、女の子は脳の前頭前野の発達時期が男の子よりも早いからです。かといって女の子の成長が男の子より早いわけではなく、男の子はその時期に側頭葉の記憶力や頭頂葉の空間認知能力がグングン育っていきます。
そのため、お母さんや大人にとって女の子は非常にわかりやすい「よい子」に見えやすく、男の子は「しつけができていない」と映りがちです。しかし、先述のお子さんの中に生活習慣がしっかりと根付く時期をゴールの目安に考えておけば、幼い時期に「どうしてできないの!」と叱り飛ばしたり落胆したりする必要はなくなります。

「しつけ」についてのまとめ
さて、繰り返しとなりますが、しつけのために一番大切なことは「生活習慣や社会マナーの家庭基準を明確にもつ」ということです。そして、それはご夫婦二人で作り上げた基準であり、決して「世の中一般の当たり前」などではないのだ、という意識も同時にもつことが大切です。
家庭基準の作り方は、「子どもがひとり立ちした時に、生きていきやすい習慣かどうか」を考えます。「生きていきやすい」ということは「自分勝手にわがままのし放題」という意味ではありません。その習慣が身に付いていれば人と良い関係を作れる、とか、健康が維持できる、とか、楽しい時間が増える、とか、生活が安定するなど、お子さんにとって貴重な財産となる習慣です。
また、親の価値観は、更にその親から学んだものである場合がほとんどですが、家庭の基準を作る前に、自分が受け継いだ価値観は本当に子どもに伝えていきたいものか吟味してみましょう。
自分が両親に対して「本当はこうして欲しかった」と心の奥深くで願っていたことはないでしょうか? 両親の豊かな愛情に心から感謝して育った人はそのままでよいと思いますが、もし両親の価値観に対して疑問を抱き続けていた部分があれば、今こそ解きほぐし我が子に対して修正した価値観を伝えていきましょう。
「しつけ」を考える実践方法
まずは、下記の項目を参考に基本的生活習慣の家庭基準を明確にしていきましょう。
・朝は何時に起きますか?
・就寝時間は何時にしますか?
・ハミガキはいつ行いますか?
・食事に関するルールはどうしますか?
・一日に何キロくらい歩きますか?
・TVをつける時間はいつですか?
・部屋の掃除はいつ行いますか?
・水回りの掃除はいつ行いますか?
・洗濯する時間帯は何時頃ですか?
・洗濯物をたたむタイミングはいつですか?
・脱いだ衣類はどこにどう片付けるか家庭内のルールは決まっていますか?
子どものしつけを考える前に、まず親がどう暮らしたいかを明快にすることが大切です。それができて初めて、子どもの暮らしを家庭基準に近づけていくスモールステップが見えてきます。
仕事に出勤する時間、通勤距離、出張の頻度、お稽古事のスケジュールなど、各家庭で事情は様々です。よって、まずは無理のない範囲で、「理想の家庭基準」と「これだけは最低限絶対守る基準」の二つを考えてみましょう。
例えばお仕事の忙しいお父さんなら「1週間に一度、休日の朝食だけは必ず家族と食卓を囲む」とか、掃除が得意な方だったら水回りの掃除は毎晩就寝前の習慣だったり、逆に苦手な方だったら「毎週水曜日は水回り掃除の日」などと決めてみましょう。
次に、「お子さんにさせよう」という意識は捨て、お母様、お父様が「生活習慣家庭内基準」を可能な限り守りましょう。家事や身支度を「つまらない作業」だと思わずに、「お子さんを自立に導く貴重な時間」と考えて、ご両親が行う姿を見せ続けましょう。
お子さんに強制せずに見せ続けることが、お子さんの中に本当に望ましい習慣の種を深く植えつけていきます。ただし、できない日があっても決して自分を責めないことが大切です。ぜひ、生活習慣家庭内基準の実践を楽しみながらおこなって下さい。

#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児












.jpg&w=256&q=75)