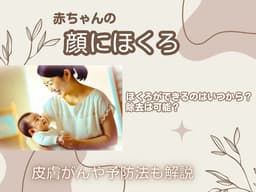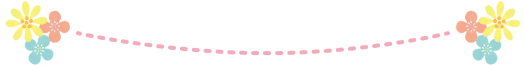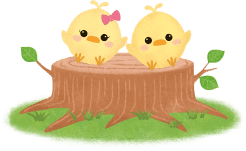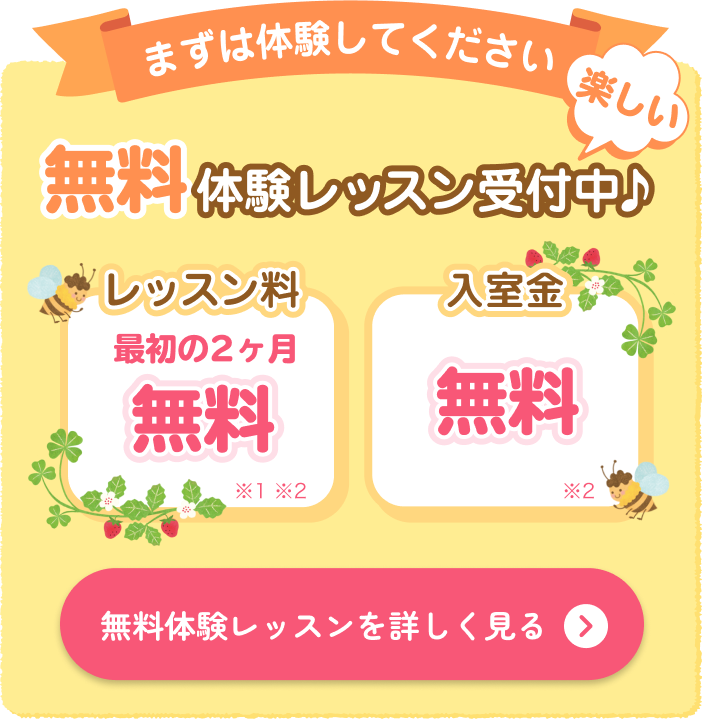夜泣きとは?
「夜泣き」とは、赤ちゃんが夜中に突然目を覚まして泣き叫ぶことです。6か月〜1歳半の赤ちゃんによく見られ、夜泣きのピークは7か月〜9か月ごろだといわれています。抱っこをしたりオムツを交換したりして泣きやむ場合もありますが、夜泣きのはっきりとした原因はわかっていません。夜泣きが激しい赤ちゃんの中には、一晩中泣き叫び続けている子もいます。
2歳を過ぎても夜泣きをくり返す子もいるいっぽうで、夜に1度も目を覚まさない赤ちゃんもいます。夜泣きの程度は、かなり個人差も大きいものです。
また、夜泣きの原因は赤ちゃんにより異なるので、確実な対処法がないのもつらいところですよね。しかし、夜泣きは永遠に続くものではありません。「ママやパパの愛情が足りないのでは?」と心ない意見もありますが、これはまったくの無根拠。赤ちゃんは「泣くことが仕事」であり、決してママやパパを困らせたくて泣いているのではありません。
国によって「夜泣き」の概念が違う
国によっては「夜泣き」という概念すらないところもあるようです。たしかに、赤ちゃんが昼間に泣くことを「昼泣き」とはいわないので、よくよく考えればうなずける話ですよね。
国民のほとんどが「赤ちゃんは泣くのが仕事だ」と容認してくれれば、夜泣きに悩むママやパパが今よりグッと減るかもしれません。
しかし日本では、まだまだ赤ちゃんの夜泣きに対して厳しい意見をあげる人もいます。とくに育児経験のない人との間には、理解の深さに大きな差が出ているようです。
「早く泣きやませないとご近所さんに迷惑がかかる!」と焦り、プレッシャーにさいなまれるママやパパは少なくありません。昼間のようにゆっくり対応できないからこそ、夜泣きの原因や対処法を知り、赤ちゃんへの理解を深めておくことが大切です。

0歳児の夜泣きの原因
赤ちゃんの夜泣きは、実ははっきりとしたメカニズムがわかっていません。そのような中で、以下の2つが原因として考えられるのではないかといわれています。
体のどこかに不快感を感じている
赤ちゃんが不快に感じることは、具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 暑い・寒い
- おなかが空いた
- のどが渇いた
- 鼻がつまっている
- オムツが汚れている
- どこかが痛い・かゆい
- 洋服や布団の肌触りが気持ち悪い
赤ちゃんは自分が感じる不快感を「泣くこと」で大人に伝えています。成長していくうちに夜泣きが減るのは「不快感を言葉で伝えられるようになるから」という考えもあるようです。
0歳児はまだ言葉を話せないので、何かを不快に感じても「泣くこと」でしか周囲に伝えられません。赤ちゃんが夜中に泣いてしまうのは、体のどこかに不快感を感じているか、何か助けてほしいことがあるケースが考えられます。
眠りが浅いためすぐに目が覚めてしまう
赤ちゃんは脳の発達を促すため、レム睡眠の割合が大人より多いことがわかっています。レム睡眠とは、昼間に受けた脳への刺激を整理する浅い眠りのこと。赤ちゃんは睡眠中も脳をはたらかせて、一生懸命頭の中を整理しているんですね。
大人はレム睡眠とノンレム睡眠の割合が2:8なのに対して、赤ちゃんのレム睡眠とノンレム睡眠の割合は5:5といわれています。
また、大人には規則正しい生活を送るための「体内時計」が備わっていますが、0歳児はその機能が発達しきっていません。昼と夜の区別がつかない場合がほとんどで、昼夜問わず寝たり起きたりをくり返します。中には昼だと思って起きたら夜で、そのギャップに驚いて泣いてしまう赤ちゃんも。昼間に感じた「不快なこと」や「怖かったこと」を思い出して、夜中に泣き出してしまうケースもあります。
一般的に、赤ちゃんの体内時計は生後4か月~3歳ごろにかけて発達していくといわれています。成長に合わせてだんだんまとまった睡眠が取れるようになってくるので、少しずつ夜泣きも減ってくるはずです。
0歳児の夜泣きの対処法
はっきりとした原因がわからない夜泣きは、対処法に困ってしまうことも多いですよね。「昨日は泣きやんだのに、今日は泣きやまない……」ということも十分に起こり得るでしょう。夜泣きの対処法はさまざまありますが、残念ながら「確実にこれが正解」というものはありません。
もしも夜泣きに困ったときは、以下の方法を複数試してみましょう。

体内時計の発達をサポートする
赤ちゃんの生活サイクルを整えるのは大人の役目です。先ほど紹介したように、赤ちゃんは体内時計が未発達のため、昼と夜の区別がつかず泣いてしまうことがあります。そのため、赤ちゃんが夜ぐっすり眠れるように、大人が体内時計を整えてあげることが大切です。
具体的には、昼間はカーテンをあけて太陽の光を浴びせ、夜間は暗くして昼と夜の区別をつけやすくしてあげましょう。なるべく食事や入浴の時間を同じにすると、生活サイクルはさらに整いやすくなります。
お昼寝はほどほどにする
大人でも昼間にたくさん活動をすると、疲れて夜眠くなりますよね。赤ちゃんも同じで、昼間にたくさん刺激を受けると体や脳を休ませるため夜は自然と眠くなります。よって、たくさんお昼寝をして昼間の活動をセーブしてしまうと、刺激が足りずに夜目を覚ましてしまうことが増えてしまいます。
夕方まで寝てしまうと夜に目を覚ましやすくなるので、お昼寝は明るい時間にすませるように心がけましょう。体内時計の観点からも、お昼寝は部屋を明るいままするのがおすすめです。
赤ちゃんと一緒にお昼寝をする
赤ちゃんのお昼寝はほどほどがおすすめですが、ママやパパはしっかりお昼寝をしてください。
昼間に赤ちゃんが寝たときは、ママやパパが何かやっている途中でも、なるべく一緒に睡眠をとるようにしましょう。
早起きをして朝ごはんをつくり、掃除、洗濯、育児、買い物……など、とにかくやることがてんこ盛りのママやパパ。それでいて一晩中続く夜泣きに毎日対応していては、体調を崩しても不思議ではありません。
昼間の家事はほどほどにして、赤ちゃんと一緒にお昼寝という名の休息をとりましょう。そうすることで夜間に必要な体力を温存でき、夜泣きの対応もいくらか楽になるはずです。睡眠は心身の健康の源。お昼寝に罪悪感を持つ必要は少しもありません。休めるときにしっかりと休んで、夜泣きに備えましょう。

入眠しやすいルーティンをつくる
「寝る時間ですよ」の合図をつくっておくと、赤ちゃんは入眠しやすくなります。たとえば、以下のようなものがルーティンとして取り入れやすいでしょう。
- 子守唄を歌う
- 絵本を読み聞かせる
- 寝る前に同じ手遊びをする
- 抱っこして背中をトントンする
赤ちゃんは、規則正しい生活サイクルがまだ身についていません。入眠前に合図を出してあげることで「今から寝る時間だ」と認識し、自発的に眠りやすくなります。
赤ちゃんが過ごしやすい温度・湿度に保つ
少しでも夜泣きを減らすためには、赤ちゃんが過ごしやすい温度・湿度に保つことが大切です。冬場は乾燥にも注意し、加湿器などで湿度をあげる意識を持ちましょう。適切な湿度を保つことで、赤ちゃんの不快感であるお肌や喉の乾燥を防げます。
また室温だけでなく、赤ちゃんの服装も暑すぎず・寒すぎずの状態を保つことが大切です。赤ちゃんが汗をかいている場合は、洋服の枚数を減らしてあげると、夜泣きがピタッと泣きやむことがありますよ。掛け布団のかけすぎも暑くて不快に感じてしまうことがあるので、赤ちゃんの様子をみながら調節してみてください。
授乳をして喉の渇きを防いであげる
赤ちゃんは体内に水をためておく機能が未熟なため、大人より喉が渇きやすくなっています。寝汗をかきやすいのも、夜中に喉の渇きで目を覚ましてしまう原因のひとつだといえるでしょう。
「喉が渇いた」と赤ちゃんが夜泣きをしてしまうときは、授乳をして喉の渇きを潤してあげることが大切です。寝汗による水分不足の防止のため寝る前に授乳を済ませておくのも、夜泣きの対処法としておすすめです。
.jpg&w=2048&q=75)
抱っこや笑顔を見せて安心させる
「おなかが空いているのかな?と思って授乳をしようとしたら、ミルクを飲む前に眠ってしまった」というママの声をよく聞きます。赤ちゃんはママから抱っこされるだけで安心感を得られ、安心して眠りにつけるケースがあるようです。
夜泣きがよく見られる生後6か月ごろから、赤ちゃんは少しずつ人の表情を認識できるようになります。ママが見せた笑顔に安心して泣きやむ赤ちゃんもいるので、夜泣きの際は積極的に笑いかけてあげましょう。
その際、背中を優しくトントンしてあげると、赤ちゃんはさらに安心できます。0歳児は言葉がわからないぶん、たくさん抱きしめたり笑いかけたりして、愛情を伝えてあげることが大切です。
オムツを交換する
うんちやおしっこでオムツが汚れていると、赤ちゃんは不快感で夜泣きをすることがあります。赤ちゃんが夜泣きをしたときは、まずはオムツが汚れていないかチェックしてみましょう。
排せつをしていなくても、夜中にびっしょりとかいた寝汗でオムツが蒸れて不快な気分になっていることがよくあります。その場合は、汚れていなくても新しいオムツと交換しましょう。
夜寝かしつける前に、うんちやおしっこでオムツが汚れていないかを確認しておくと、夜泣きの防止につながります。
赤ちゃんが安心できる音を聞かせる
産まれて間もない赤ちゃんは、どんな音でも新鮮に聞こえるものです。0歳児は日々いろいろな音に刺激を受けて、耳や脳が疲れやすい状態になっています。何かに不快感を覚えて夜泣きをしてしまうときは、赤ちゃんが安心できる音を聞かせてリラックスさせましょう。
たとえば、赤ちゃんが安心できる音には、以下のようなものがあります
- 水が流れる音
- テレビの砂嵐音
- ビニール袋のクシャクシャ音
上記はママのおなかにいたときの音に似ているそうで「赤ちゃんが安心できる音」として広く認識されています。最近は赤ちゃんが安心する音を集めたアプリもあるようなので、夜泣きに困ったら試してみてもいいかもしれませんね。
思いきってしっかり起こす
赤ちゃんが元気に夜泣きを続けるときは、日中に遊び足りずエネルギーがあり余っている状態になっているかもしれません。そのような場合は、無理に寝かしつけるより思いきって遊んであげた方がすんなり寝てくれるケースもよくみられます。
他の対処法を試してうまくいかなかったら、思いきって部屋を明るくして短時間グッと集中して遊んであげましょう。赤ちゃんは「泣くこと」以外に「寝ること」も仕事なので、遊び疲れたらぐっすり眠りについてくれるはずです。遊び終わったら、オムツのチェックや授乳も忘れずにおこないましょう。
.jpg&w=2048&q=75)
外の空気に触れさせる
昼間にあった「不快なこと」や「怖かったこと」を思い出して、夜泣きをくり返してしまう赤ちゃんもいます。そのような場合は、夜風にあたりに行ったりドライブに出かけたりして、思い出した嫌な記憶をやわらげてあげることが大切です。
外部から刺激を与えることで、他のことに気を取られて泣きやむケースも多々あります。とくにドライブのように振動が加わるものは、おなかの中にいた頃を思い出すようで安心する赤ちゃんが多いようです。
ママやパパの気分転換にもなるので、余裕があればぜひ試してみてください。
まとめ:夜泣きの卒業まで見守ろう
一生懸命成長しようと日々奮闘している赤ちゃんは、どうしてもママやパパに対するお願い事が増えてしまいます。しかしそれは、赤ちゃんがたくましく生きようと、立派に成長している証拠でもあるんです。
「どうして泣きやんでくれないの?」
「早く泣きやませなきゃ」
と焦った姿を見せてしまうと、赤ちゃんはママやパパの焦りを感じとり、不安でさらに泣き続けてしまいます。
夜泣きはいつまでも続くものではなく、成長の過程でいつかは卒業するもの。愛おしい我が子の寝顔をずっと守っていけるように、つらい夜泣きが続いた際はぜひ今回紹介した対処法を試してみてくださいね。
.jpg&w=2048&q=75)
#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児
.jpg&w=2048&q=75)



.png&w=256&q=75)




.jpg&w=256&q=75)