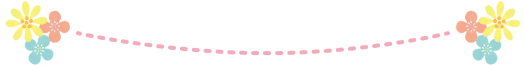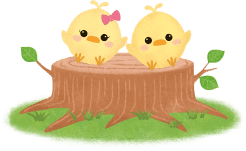ハイハイってどんな運動?

まずは、「ハイハイ」とはそもそもどんな運動なのか?、についてです。似たような運動として、「ズリバイ」や「高這い」といった単語もよく聞くと思いますので、違いについて以下に簡単に掲載します。
◆ズリバイとは?
ハイハイの前段階にあたり、腹ばいで移動するほふく前進のような動きです。
◆ハイハイとは?
両手で上半身を支え、ひざ立ちで腰とお尻を持ち上げて前進する動きです。
◆高這いとは?
ひじとひざが伸びた状態でハイハイをする動きです。
ハイハイには色々な種類があるんだね♪それぞれの段階で違う動きをしていることがよくわかるね。

ハイハイはいつから始めたらいいの?

脳が育つ0歳期に近ければ近いほど良いのは言うまでもありません。早くハイハイが始められればそれだけ早く身体発達が促進されますし、脳の発達にも良い影響があると考えられます。
とはいえ焦る必要はありません。できるだけベビーマッサージをしてあげ、ハイハイに誘うような動きを色々取り組んであげれば比較的早くハイハイをしてくれるようになるでしょう。
具体的にはうつぶせ状態で、目の前に赤いボールなどを置いてあげて、足の裏に手を添えてあげます。そうするとこちらの手を蹴って前へ進む感覚を身につけてくれやすくなります。そのように意図してハイハイをさせてあげるような工夫をしましょう。しっかりハイハイの時期を過ごして歩くようになってくれることを期待しましょう。
お子さんがハイハイせずに歩いた方もどうぞご心配なさらないで下さい。
2歳くらいまでは、お子さんの脳は凄まじい勢いでシナプス回路の編成を進めています。筋力はまだまだこれからいくらでも育てることが可能だからです。 しかし、やはりできれば、少しでも早い時期にハイハイができたほうがお子さんのためになります。
身体発達に良い影響があるなら、今からでもお子さまと一緒にハイハイをして遊びたいですね♪
.png&w=256&q=75)
ハイハイは何歳頃までするといいの?
何歳まででも構いません。動物の真似をして4つんばいになって歩くような遊びは大いに結構だと思います。股関節の最終的な完成は平均して男の子で15歳、女の子で13歳です。ハイハイ運動は身体能力のみならず、心に深くかかわる中脳や間脳を正しく育て、大脳前頭葉を大きく発達させます。人生の中で脳の発達速度が凄まじい8歳9歳頃までは、たっぷりと這う遊びをさせてあげて良いと思います。
ハイハイにまつわる現状について
人間がおこなう運動のすべては、いくつかの基本となる別々の運動能力(目や手・足など)が複雑に組み合わされている協応運動だということがいえます。
ベビーパークでは、もっとも基本的な運動能力とは【懸垂力】【支持力】【バランス能力】【跳躍力】の4つだと考えています。そして、ハイハイは【支持力】を大きく成長させる運動です。
ハイハイをしない事で【支持力】が発達しない現代
ハイハイによって育つ【支持力】とは、腕を伸ばして体を支える能力のことです。
昔に比べて現代の子ども達は様々な運動能力が低下しており、その中でも支持力はもっとも失われつつある能力です。ハイハイの時に使う筋肉は上腕三頭筋(わきの裏側にある筋肉)と三角筋(力こぶで膨らむ筋肉の反対側にある筋肉)です。力こぶの上腕二頭筋に比べると、意識されにくい筋肉です。
ハイハイをすることで自らの体重を腕で支える力が培われ、バランスを崩して転びそうになった時、あるいは何かにぶつかりそうになった時など、私たちが身体的な安全を守る時に大変重要となります。バランス能力が適切に働くと、頭や体を守るためにとっさに手が出て体を支えることができます。
しかし、自分自身を支える力が育っていないと、せっかく手が動いても結局は怪我をしてしまいます。例えば最近の大学生は、ちょっと雑巾がけをしたら手首をねんざしてしまった、という事例が後を絶ちません。雑巾がけの高さ、すなわち自分の腕の長さ程度でねんざですから、転んだ場合はただそれだけで骨折事故が多発しています。
このように乳幼児期に支持力が適切に育つ環境にないと、骨折やねんざどころか手が出ることすらない、という子どもに育ってしまいます。
昔の生活環境にはあって、今の生活環境にないもの
かつての日本の生活は、支持力を育てるのに非常に適していました。主に畳の生活では、立ち上がる時に自然に手をついて体を支えます。子ども達は床でジャレあい、兄弟で取っ組み合いの遊びをし、親が特別な身体教育など考えなくても普通に支持能力を育てていきました。
しかし、現在のようにフローリングの洋室中心の家造りが一般的になってしまった環境では、かつての日本の生活で自然に身についた力が今はもう育ちません。それを常に考えて、子どもの身体発達が適切に伸びるための支援をしなければなりません。

ハイハイの経験がないのは個性?
支持力を育むもっとも重要な時期に、「ハイハイの習慣」が失われつつあります。
昔の日本でハイハイを経験することなく二足歩行を始めてしまう子どもは、ほとんどいませんでした。生まれてからずっと畳の上で布団で寝ているので、動くことを覚えれば自然とハイハイしてしまうものだったのです。
しかし、今はハイハイを経験することのない赤ちゃんは急増しており、最近では「それも一つの個性」や「赤ちゃんの正常な発達の一つの形」だとまでいわれています。
確かにハイハイしなくても、その後ご両親やあるいはお子様本人がものすごく頑張り、ほかの子ども達よりもたくさん脚や腕の筋肉を使う生活環境を作り出せば、運動能力は発達するでしょう。
ですが、幼稚園期・小学校期も積極的な運動習慣がなかったら「人間としての基礎的な体を守る身のこなし」や「身を守るだけの筋力」が育ち損ねてしまいます。現代社会の生活環境では、エレベーターなど便利な道具の普及にともなって、普通に生活していたら適切な身体能力は育たないのです。
大切なことは「ハイハイしたかしないか?」ではなく、「0歳から成長期において、適切な筋力と、運動に必要な脳の回路が育つだけの経験を与えたかどうか?」です。
乳幼児期にたくさんハイハイをすることで、人間が歩き始めるまでの自然な発達段階を進むための筋肉や骨の正常な発達を促すので、幼児期以降の高度な運動能力の成長も期待しやすくなります。
ハイハイをするまでの取り組みのご紹介

そんな子どもの成長に非常に重要なハイハイを促すための方法をご紹介します。
もっとも大切なことは【「うつ伏せ」の姿勢を好きにさせること】です。
・お母さまがあおむけに寝て、お母さまの胸の上でお子さまをうつ伏せ姿勢にして過ごしましょう。歌を歌ったり頭や背中をなでたりするのも良いですね。
・まだハイハイしないお子さまや、うつ伏せが嫌いなお子さまには、「お母さまの胸の上でうつ伏せで過ごす」という機会を増やしましょう。
・ハイハイしているお子さまには、できるだけ一日中、床の上で安全に過ごせるように部屋の模様替えをしたりお子さまが触ると困るものを収納するなどの環境を工夫してあげてください。
ハイハイをすると、どうなるの?
子どもの身体が適切に育つ旬の時期に、旬の教育を与えることが大変重要なことは皆さんご存じのとおりです。人間は、まずズリバイをし、ハイハイをし、そして高這いができるようになってから歩き始めるというのが自然な発達の順番です。この発達の順番が実はとても大切なのだという事を知っておいてほしいと思います。特にハイハイをする時期は大変大切な時期であると考えられています。
ハイハイをすることによって非常に良く育つ身体部位が3つあります。
【股関節】が発達する
1つ目が、「股関節」です。
生まれたばかりの赤ちゃんは、股関節がほとんど形成されていません。
(股関節のソケット部分、つまり大腿骨の骨が収まる穴がほとんどなく、太ももの骨の一番上の部分は、ごく浅いくぼみに軽く収まった形になっています)
ハイハイする機会をたくさん与えられた赤ちゃんがズリバイをおこなうと、大腿骨が股関節のくぼみを横からこするような形で動きます。 次第に赤ちゃんが高這いできるようになると今度は大腿骨の先端がくぼみを縦の方向にこするように動きます。こうして縦と横の両方から刺激を受けながら適切に股関節が形成され、様々な方向に脚が動くようになるのです。
ハイハイを十分にしないで歩いた子どもが転びやすいなどと言われるのにも、一つは股関節の発達・形成が未熟になるからということが言えます。ハイハイと股関節形成の関係が科学的に解明されていくには、まだ長い時間を必要とするのでしょうが、少なくとも50年前の日本では乳児の股関節脱臼の発症率は大変低かったようです。それは日本の住環境や子育て環境が、ハイハイをする時間をしっかりとるのに適していたという事と関係あると考えられます。
ハイハイを十分にさせたくても、苦手なお子さんもいらっしゃいます。そんなときは、ベビーマッサージの回数を増やしてあげましょう。ベビーパークレッスンではマッサージの具体的な方法をお伝えしておりますが、ベビーマッサージというのは大変有効な方法です。
【伸筋】が発達する
2つ目が、前述の支持力にかかわる「身体を支持するために重要な筋肉=伸筋」です。
関節を動かす筋肉は、伸筋と屈筋に分けることができます。
伸筋はものを投げたり押したり、打ったりするときに使います。野球やサッカー、バスケットボール、テニス、ゴルフなど、球技には伸筋が重要なものが多いです。
屈筋は、ものを持ち上げたり引っ張る時に使います。重いものを持ち上げるときは屈筋しか使いません。 実は人間の筋肉というものは、屈筋よりも伸筋の方が遥かに強力です。重力に逆らって二本足で立っていられるのも、伸筋のおかげなのです。
2つ目が、前述の支持力にかかわる「身体を支持するために重要な筋肉=伸筋」です。
関節を動かす筋肉は、伸筋と屈筋に分けることができます。
伸筋はものを投げたり押したり、打ったりするときに使います。野球やサッカー、バスケットボール、テニス、ゴルフなど、球技には伸筋が重要なものが多いです。
屈筋は、ものを持ち上げたり引っ張る時に使います。重いものを持ち上げるときは屈筋しか使いません。 実は人間の筋肉というものは、屈筋よりも伸筋の方が遥かに強力です。重力に逆らって二本足で立っていられるのも、伸筋のおかげなのです。

【脳~中脳・間脳・前頭葉~】が発達する
3つ目が、「脳~中脳・間脳・前頭葉~」です。
体を動かす時にもっとも重要な働きをしている のは「脳」です。
「脳」「神経」「筋肉」「骨」の見事な連携によって、私たちの体は高度に動きます。私たちの身体能力・運動能力を高めるためには、脳も神経も筋肉も骨も適切に育てる必要があります。そして脳が凄まじい勢いで成長するのは、まさに 0~3歳期なのです。筋肉と骨の支持力。支持運動に必要な複雑な信号を発信するための脳回路。ハイハイの動きは支持運動に必要なすべての脳回路・神経・ 筋肉・骨を育てることに役立ちます。
これは最新の脳科学でもまだ解明されていないことなので、あくまで仮説としかいえませんが、大切なことなのでお伝えしておきたいと思います。脳の発達が未熟な新生児がハイハイできるようになるためには、延髄や小脳、 間脳、中脳が発達することが不可欠です。中脳が発達することでハイハイできるようになり、またハイハイすることで中脳やそれに繋がる間脳も育つと考えられています。間脳では本能、本性、反射をコントロールしています。
つまり中脳や間脳が発達していなかったら、ハイハイもできませんし、逆にハイハイすることで脳の発達につながると考えられるのです。これらの脳の発達が順調に進まないと、成長してからの自己感情コントロールが困難になるといわれています。
さらにハイハイの動きは、人間の知性の座である前頭葉も発達させるといわれています。指先の細かい動きよりも、大きい筋肉を動かす時の方が、脳の多くの部位がいっせいに強く動くのです。計算テストの前に軽い全身運動を行うと平均点が上がるという研究結果の報告もありますから面白いですね。
合わせて読みたい
ハイハイをする時期に注意すること
ハイハイは赤ちゃんの成長過程において重要なステップであり、多くの親にとって待ち望まれる瞬間です。この時期には、赤ちゃんが新しいスキルを習得するだけでなく、自立心や探求心も育まれます。しかし、ハイハイの時期にはいくつか注意すべき点があります。
以下に、赤ちゃんがハイハイを始める時期に気を付けるべきポイントを解説します。
1. 安全な環境を整える
ハイハイを始める前に、まず赤ちゃんが安全に動き回れる環境を整えましょう。家具の角にクッションをつけたり、小さな物や危険な物を片付けたりすることが重要です。また、階段やベランダへのアクセスを防ぐためにベビーゲートを設置しましょう。
2. 体力と筋力のサポート
ハイハイには赤ちゃんの筋力と体力が必要です。腹ばいで遊ばせる時間を増やし、赤ちゃんが自分の体を支える練習をさせましょう。おもちゃを使って前方に動かす動きを促すことも効果的です。
3. 見守りと声かけ
ハイハイの練習中は、赤ちゃんが安全に楽しめるように見守りましょう。また、赤ちゃんに声をかけて励ますことで、安心感と自信を与えることができます。「すごいね!」「上手だね!」といったポジティブな声かけを心がけましょう。
4. 健康状態のチェック
赤ちゃんの健康状態を常にチェックし、異常がないか確認しましょう。特に、ハイハイ中に異常な姿勢や動きを見せる場合は、小児科医に相談することをお勧めします。また、定期的な健康チェックアップも欠かさずに行いましょう。
5. 個々のペースを尊重
赤ちゃんの成長には個人差があります。ハイハイを始める時期やペースは赤ちゃんそれぞれ異なるため、他の子と比較せず、自分の子のペースを尊重しましょう。焦らずに、赤ちゃんが自然に成長するのを見守ることが大切です。
6. 楽しい環境づくり
ハイハイの練習は、赤ちゃんにとって楽しい時間であるべきです。カラフルなおもちゃや柔らかいマットを用意して、赤ちゃんが楽しみながら運動できる環境を作りましょう。また、親も一緒に遊ぶことで、親子の絆を深めることができます。
ハイハイは赤ちゃんの成長における重要なステップです。この時期に適切な環境とサポートを提供することで、赤ちゃんの健康的な発達を促すことができます。親として、赤ちゃんの成長を見守り、サポートすることに喜びを感じながら、楽しい育児の時間を過ごしましょう。
ハイハイに関するよくある質問
・うつ伏せの姿勢を好きにさせる
・お母さんの胸の上でうつ伏せにする
・うつ伏せの機会を増やす
・安全な遊び環境を整える
股関節の発達:ハイハイにより、赤ちゃんの股関節が適切に形成され、様々な方向に脚が動くようになります。
伸筋の発達:身体を支える重要な筋肉である伸筋が発達し、物を投げたり押したりする動作に役立ちます。
脳の発達:ハイハイは脳の発達、特に中脳・間脳・前頭葉の発達に寄与し、体の動きや感情コントロールに重要な役割を果たします。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #ハイハイ #身体 #発達 #効果 #いつから

.webp&w=256&q=75)
.jpg&w=256&q=75)
.jpg&w=256&q=75)


.jpg&w=256&q=75)
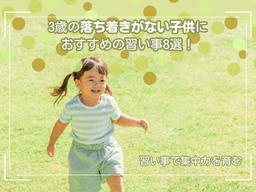





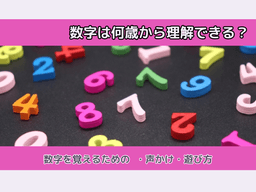

.png&w=256&q=75)