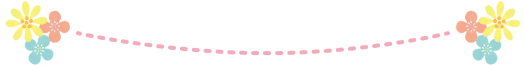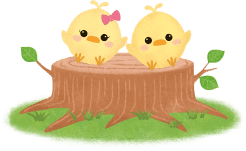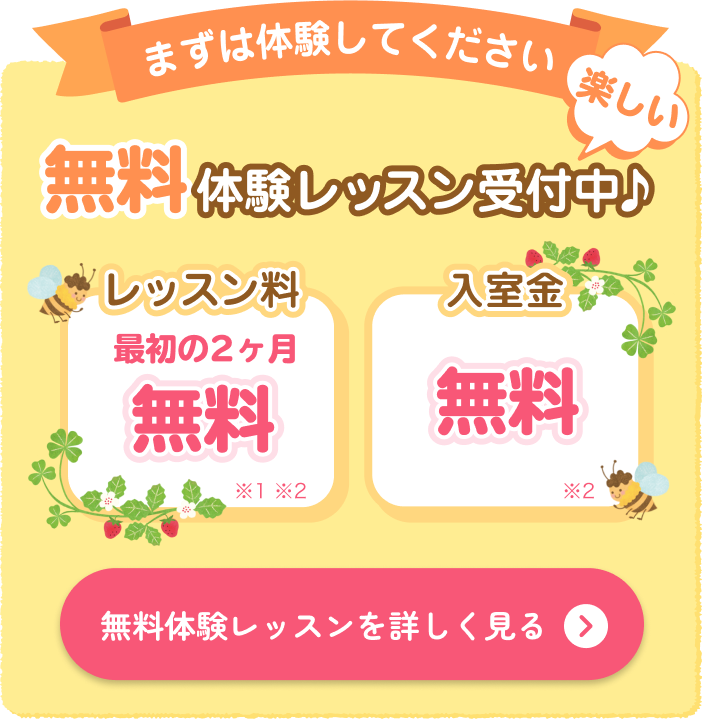自己肯定感とは?
自己肯定感とは自分を肯定して認める感覚で、能力や条件に関係なく、短所を含めたありのままの自分を受け入れて認められる感情を指します。自己肯定感の高い人は、自分に自信を持っている場合が多く、自分は必要とされている存在であると感じたり、自分を好きだと思えたりする人が多い傾向です。
自己肯定感を高く持てると、自分の今後の人生における可能性を信じ、さまざまな物事に対して積極的に取り組める原動力が得られます。また人間関係を築くうえでもプラスに働く場合が多いため、生きていくうえでより幸福感を感じやすいでしょう。
自己肯定感の高さは成長の過程で育つとされており、自己肯定感の高い人は子ども時代に親から受けた言動に大きく左右されます。
幼いころに関わる「大人の言動」がその子の将来の自己肯定感に影響を与えるんだね!

自己肯定感が低いとどうなる?
自己肯定感が低いと、どうしても自分をダメな人間だと考えてしまいがちです。結果として、物事をネガティブにとらえてしまい、すぐにあきらめてしまったり、無気力になったりする場合が多くなります。
また自分に自信が持てないため、生きていくうえでも壁にぶつかりやすく、人間関係にトラブルを抱えやすかったり、他人と比べては落ち込んでしまったりするなど、生きづらさを感じてしまう場合も多くなります。
自己肯定感は、特に子どもの頃に親からどう接されたかが重要な要因であり、成長過程によって高くも低くもなります。
自己肯定感が低い子どもの特徴
一般的に、自己肯定感が低い子どもには次のような特徴があります。自己肯定感が低い子どもの特徴として三つを取り上げて紹介します。
◇自己肯定感が低い子どもの特徴三つ
1. 成功を喜べない
2. 自分を責めてしまう
3. チャレンジ精神がない
以下、三つの自己肯定感が低い子どもの特徴を説明します。
1. 成功を喜べない
自己肯定感が低い子どもは、自分を素晴らしい存在、価値ある存在だとは感じられないため、褒められても素直に自分の成功を喜べません。
褒められたときでも、親から本気で褒められていないのではないかと感じてしまい、褒められても素直に受け入れられない傾向にあります。
2. 自分を責めてしまう
自己肯定感が高い子であれば、叱られた場合でも次に失敗しないための原動力にできるかもしれません。しかし自己肯定感が低い子は叱られたことに対して自分を責めてしまい、必要以上に落ち込んでしまう場合が多くなります。
結果として「どうせ僕なんて何をやってもダメな人間なんだ」と思い、常に自分に自信がない状態に陥りやすくなります。
3. チャレンジ精神がない

自己肯定感の低い子は自分に自信がないため新しい物事になかなかチャレンジしようとしません。行動する前から「やってみても無理だろう」とすぐに諦めてしまう場合が多くなります。
また、失敗を恐れているため、無関心を装い、最初から挑戦をしない場合もあります。
子どもの自己肯定感を高めるには?
自己肯定感を高めると、子どもは自分の価値や力を信じて生きていけるため、何事に対してもチャレンジ精神を持って前向きに取り組めるでしょう。子どもの自己肯定感を高めるには、子どもに対する親の関わり方も考える必要があります。
子どもの自己肯定感を高めるための方法として、次の三つを取り上げ、紹介します。
◇子どもの自己肯定感を高めるための方法三つ
1. 子どもを否定せず、全てを受け入れる
2. 子どもをほめる
3. 周りと比べず、少し前の自分と比べる
以下、三つの子供の自己肯定感を高めるための方法を説明します。
1. 子どもを否定せず、全てを受け入れる
子どもの自己肯定感を高めるためには、子どもを否定するような発言をせず、ありのままの姿を認めることが必要となります。
もし子どもが失敗したり間違ったりした場合でも、「なんで失敗したの」「どうしてできなかったの」などと否定する声かけしないで、「頑張ったんだから大丈夫」「次にまたチャレンジしてみようよ」と伝えてみる、子どもにできない場合があったときでも怒らず、「そのままのあなたでいいんだよ」と話してあげましょう。
子どもの全てを受け入れる関わり方をすると、子どもは自分を「ダメな人間だ」と考えるようなことはありません。そして「それでは次に同じ失敗をしないためにはどうしたらいいのか」と前向きな考えを持てます。前向きな考えは、生きるための原動力となり、新たなチャレンジ精神をも生み出します。
2. 子どもをほめる
子どもの自己肯定感を高めるには、子どもをほめるのが大切です。子どもはほめられると素直な気持ちになり、相手に対して信頼感を持つようになります。同時に、他者に対しても優しい感情を持てるようになり、人のためにもっと役立ちたいと思えるようになるでしょう。
子どもの自己肯定感を高めるには、ほめるときにも子どもを一人の人間として尊重するようなほめ方が重要となります。結果だけをみてほめたり、親の期待にだけこたえてくれたときだけほめたりするほめ方は、子どもの自己肯定感が低くなってしまいます。
能力や結果だけを見てほめるのではなく、子どものがんばりを認めるようなほめ方をするようにしましょう。

3. 周りと比べず、少し前の自分と比べる
親はついつい周りの子どもと自分の子を比べてしまいがちになりますが、周りの子と比べてほめるのはおすすめできません。周りの子と比べてほめられた子は、どうしても他人の評価を気にする子になってしまいます。
子どもの自己肯定感を高めるためには、周りと比べるのではなく、少し前の自分と比べるようにしましょう。前はできなかったことができるようになったと子どもは自分の以前と比較しての成長を認めてもらえると、満足感を得られるようになります。結果として、子どもは新たな挑戦に対して前向きな気持ちで取り組めるようにもなっていくのではないでしょうか。
大人側の意識を変えて的確に接してあげることがとても重要だということがわかるね。

合わせて読みたい
自己肯定感を高めるのにやってはいけないことはあるのか
子どもの自己肯定感を高めるために、親として子どもにやってはいけないことがあります。子どもの自己肯定感を高めるためには、どのような点に気を付け、子どもに接するべきなのでしょうか。
子どもの自己肯定感を高めるために親が心がけるべき内容を三つ取り上げ、紹介します。
◇子どもの自己肯定感を高めるために心がけるべき内容三つ
1. 叱らない、怒鳴らない
2. 否定しない
3. 結果を求めない
以下、子どもの自己肯定感を高めるために心がけるべき内容三つを紹介します。
1. 叱らない、怒鳴らない
叱られたり、怒鳴られたりが多い子どもは、どうしても自己肯定感が育ちにくい傾向にあります。
子どもの立場からすると、いつも叱られたり怒られたりしていると、ママは実は自分を嫌いなのかもしれない、と考えるようになり、自分に自信が持てなくなってしまう場合もあります。叱りすぎたり、怒鳴られすぎたりが多くなると、結果として、子どもの自己肯定感が低くなってしまいます。子どもの自己肯定感を高めるためには、感情的に叱ったり怒鳴ったりしないように気を付けることが必要です。
2. 否定しない

何か間違ったことを子どもがした場合に、「だからあなたはダメな子だ」と子どもを否定するような言い方をするのも、子どもの自己肯定感を下げてしまうことにつながります。特に子ども自身の存在や感情を否定するような接し方は、子どもが親に対して不信感を持つきっかけともなりかねないので注意が必要となります。
たとえ子どもの行動に納得できない点があったとしても、親は子どものありのままの感情をしっかりと受け止め、子ども自身を認めるようにしましょう。
3. 結果を求めない
子どものチャレンジしたことや頑張った内容がうまくいかなかった場合でも、結果だけをみて、ほめたり責めたりするようなことは避けましょう。重要なのは、子どもが自分からチャレンジしてみたいと思う気持ちや努力したプロセスなのです。
結果だけを求めて、できた・できていないで判断をするのではなく、結果までの過程を観察し、ほめるべきところはほめる対応をすると、子どもの自信につながっていきます。
自己肯定感が低いと生きづらさにつながることも
自己肯定感が低いと自分を否定する癖がついてしまい、物事に対して前向きな気持ちが持てなくなるかもしれません。自己肯定感の低い子どもは、常に自分に自信がなく、積極性に欠けたり、チャレンジ精神が持てなかったりする傾向に陥りがちとなります。
結果として、生きていく上でさまざまなトラブルに巻き込まれやすく、生きづらさを感じやすくなってしまう場合もあるでしょう。

【まとめ】子どもをしっかり受け入れて自己肯定感を高めよう
子どもの自己肯定感を高めるためには、子どものありのままの姿を受け止めることが大切です。子どもの全てを受け入れると、子どもは自分が大切な存在であると認識し、自信を持って前向きに生きていけるようになります。
そのためにも親は子どもの自己肯定感を高められるような接し方を心がけることが必要です。子どもの行動に対して、一方的に叱ったり否定したりするのではなく、子ども自身の感情をしっかりと受け止める、また、結果だけを求めるのではなく、努力したプロセスも観察するようにすると、子どもの自己肯定感を育てていけるようになります。
自己肯定感は、子ども時代の親からの接し方に大きな影響を受けますので、子どもの実りある人生のためにも、ぜひ日頃から子どもへの言動を意識してみましょう。
#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児













.png&w=256&q=75)